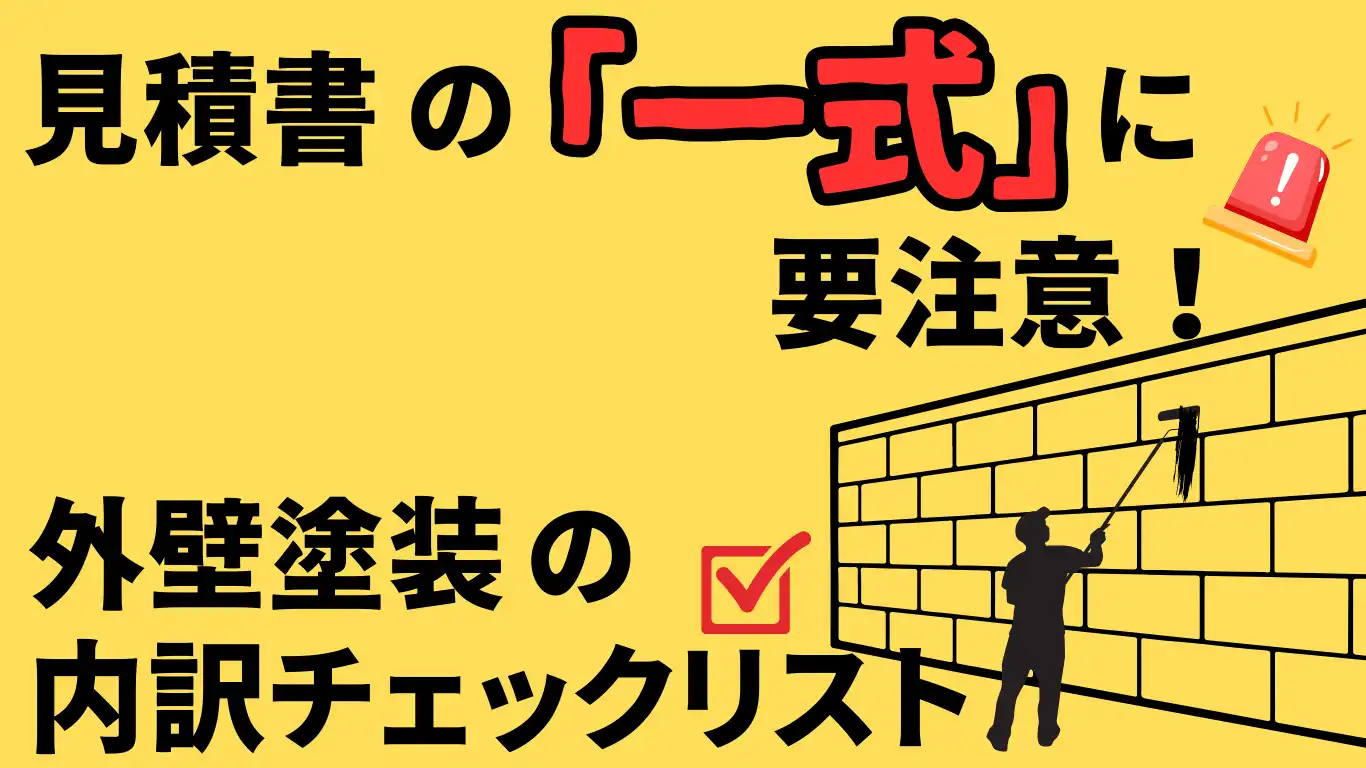
要点

外壁塗装の見積書で最も警戒すべきは、内容が曖昧な「一式」表記です。適正な価格で質の高い工事を行うためには、全ての項目を数量と単価で明確化させ、使用する塗料の仕様(メーカー名、製品名、塗装回数)を必ず記載させることが必須です。
相見積もりを比較する際は、総額だけでなく、これらの内訳が同条件になっているかを確認し、トータルコストの優位性を見極める必要があります。
見積の基本構造:費用の3つの柱

外壁塗装の見積書は、主に以下の3つの要素で構成されており、これらの要素を理解することが「一式」見積を分解する第一歩となります。
直接工事費(実行費用)
実際の施工にかかる費用で、材料費と労務費(人件費)に大別されます。これには、塗料そのものの費用、足場組立・解体、高圧洗浄、下地補修、シーリング工事、塗装作業などが含まれます。
共通仮設費(間接費用)
工事現場を維持・管理するために必要な費用です。これには、足場、養生(飛散防止ネット)、仮設トイレ、工事車両の駐車スペース確保費用などが該当します。これらの費用は、外壁塗装工事総額の**20%〜30%**程度を占めることがあります。
諸経費(管理費・間接経費)
施工業者が工事全体を管理・運営するために必要な費用です。具体的には、現場管理費、安全管理費、保険料、営業経費、利益などが含まれます。一般的に、諸経費は総額の5%〜10%程度が目安とされます。リフォーム営業会社やハウスメーカーの場合、ここに中間マージン(利益)が大きく上乗せされることがあります(リフォーム営業会社の場合、物件につき30〜40%の利益を稼ぎ出すこともある)。
内訳チェックリスト20項目《内訳チェックリスト表》

見積書で「一式」とまとめてしまいがちな重要項目を20個リストアップしました。読者はこの表を使い、業者に対し、全ての項目を数量と単価で明確に記載することを求めましょう。
| 項目 | 単位 | 必須記載内容 | OK例(明確な記載) | NG例(警戒すべき記載) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 仮設足場 | ㎡ | 足場種類、設置面積、メッシュシート費用を含むか。 | 280㎡ @ 1,200円/㎡ | 足場工事 一式 |
| 2. 高圧洗浄 | ㎡ | 洗浄方法(通常/バイオ)、洗浄回数。 | 外壁 130㎡ @ 250円/㎡(通常高圧洗浄) | 洗浄費 一式 |
| 3. バイオ洗浄 | ㎡/式 | 使用薬剤名、別費用か否か。 | バイオ薬剤散布 130㎡ @ 500円/㎡ | 特殊洗浄 一式 |
| 4. 養生(飛散防止) | ㎡/式 | 養生範囲、ネットの種類。 | 窓・床養生 130㎡ @ 300円/㎡ | 養生費 一式 |
| 5. シーリング撤去 | m | 撤去が必要な目地の長さ。 | 撤去打替 100m @ 300円/m | コーキング 一式 |
| 6. シーリング打ち替え | m | 使用材料名(製品名)、高耐久材か、プライマー塗布を含むか。 | 打ち替え 100m @ 1,300円/m(オートンイクシード) | シーリング材代 |
| 7. クラック補修 | m/箇所 | 補修方法(Vカット/Uカット)と使用材料名(フィラー等)。 | Vカットシーリング補修 5m @ 4,000円/m | 下地調整 |
| 8. ケレン/サビ落とし | ㎡/m | 範囲と工法(ケレン=素地調整)。 | 金属部ケレン清掃 10m @ 300円/m | 素地調整 一式 |
| 9. 下塗り(下塗) | ㎡ | 塗材名(シーラー/フィラー)、塗布量(規定量)。 | 〇〇シーラー 130㎡ @ 800円/㎡(1回塗り) | プライマー代 |
| 10. 中塗り(中塗) | ㎡ | 上塗り材との仕様整合性、塗回数。 | 〇〇塗料(中塗) 130㎡ @ 1,500円/㎡ | 塗装費用 |
| 11. 上塗り(上塗) | ㎡ | 塗料名・樹脂グレード・艶、塗回数。 | 〇〇塗料(上塗/フッ素) 130㎡ @ 1,500円/㎡ | 外壁塗装 一式 |
| 12. 雨樋塗装 | m | 塗料名、回数。 | 雨樋 30m @ 1,200円/m | 付帯部塗装 一式 |
| 13. 軒天塗装 | ㎡ | 塗料名(防カビ性など)、回数。 | 軒天 25㎡ @ 1,500円/㎡(2回塗り) | - |
| 14. 破風/鼻隠し塗装 | m | 塗料名、回数。 | 破風 20m @ 1,500円/m | - |
| 15. シャッターボックス | 箇所/式 | 塗装の有無、サビ止め(プライマー)の有無。 | シャッターボックス 3箇所 @ 8,000円/箇所 | - |
| 16. ベランダ防水 | ㎡ | 防水の種類(FRP/ウレタン)、塗回数。 | ウレタン防水 10㎡ @ 6,000円/㎡ | ベランダ修理 |
| 17. 基礎巾木塗装 | m | 使用塗材(基礎専用材)と回数。 | 基礎巾木 30m @ 1,500円/m | - |
| 18. 廃材処分費 | 式 | 撤去した旧シーリング材、足場解体時の廃材など。 | 廃材処分費 1式 30,000円 | - |
| 19. 現場管理費 | 式/% | 現場監督の人件費、通信費等。 | 管理費 1式 80,000円(総額の8%) | - |
| 20. 諸経費 | % | 業者利益、一般管理費。 | 諸経費 総額の 5% | - |
数量の出し方&相場レンジ
適正な単価を比較するためには、まず提示された「数量」が正しいかを知る必要があります。
外壁面積の目安算定
外壁塗装の面積(塗り面積)は、図面がない場合、延床面積を基に概算されます。
外壁面積(㎡) ≒ 延床面積(坪)×3.3㎡/坪×換算係数(1.2∼1.4)外壁面積 (㎡) \fallingdotseq 延床面積 (坪) \times 3.3㎡/坪 \times 換算係数 (1.2 \sim 1.4)
- ・換算係数(1.2–1.4):窓や玄関などの開口部が多い場合は係数が小さくなり、壁面が多く複雑な形状の場合は大きくなります。
- ・例(30坪):30坪 × 3.3㎡/坪 × 1.3 = 約129.7㎡
《数量算定早見表》単位と相場レンジ
| 項目 | 単位 | 数量算定の目安 | 相場レンジ(材料+施工費) |
|---|---|---|---|
| 足場+メッシュ | ㎡ | 建物外周長 × 高さ | 1,000円~1,800円/㎡ |
| 高圧洗浄(通常) | ㎡ | 外壁面積 | 100円~300円/㎡ |
| シーリング(撤去打替) | m | サイディング目地の総延長 | 900円~1,600円/m |
| シーリング(増し打ち) | m | 窓回りなど(既存撤去がない場合) | 600円~1,100円/m |
| 下塗り | ㎡ | 外壁面積 | 400円~900円/㎡ |
| 中塗り・上塗り | ㎡ | 外壁面積 | 1,500円~3,000円/㎡(塗料グレードによる) |
| 雨樋・破風 | m | 部材の総延長 | 800円~1,800円/m |
| 軒天 | ㎡ | 軒天の水平投影面積 | 1,000円~1,800円/㎡ |
| 諸経費 | %/式 | 総額に対する割合 | 5%~10%(別途計上の場合) |
※記載された相場価格は、地域、建物の形状、業者(自社施工か否か)によって大きく変動する可能性があります。
塗料仕様テンプレ:塗膜の品質を担保する

上塗り材の品質は、メーカー、製品名、樹脂グレード、塗布量、乾燥時間によって決まります。見積書にこれらの詳細が欠けている場合、規定量よりも塗料を薄めたり(希釈)、塗り回数を減らしたりする手抜き工事につながるリスクがあります。
必須確認項目とE-E-A-T対応
| 項目 | 確認すべき内容 | 性能根拠(出典例) |
|---|---|---|
| メーカー名/製品名 | 塗料の特定。同じシリコンでもメーカーやグレードで性能が全く異なる。 | 塗料メーカー技術資料 |
| 樹脂グレード | シリコン、フッ素、無機など。 | JIS K 5658 建築用耐候性塗料等級 |
| 艶(光沢度) | 艶あり、7分艶、5分艶、3分艶、艶消し。 | JIS K 5600-4(塗膜の光沢度試験) |
| 規定塗回数 | 下塗り1回、中塗り1回、上塗り1回の合計3回塗りが基本。 | JASS 18 塗装工事標準仕様書 |
| 標準塗布量 | 1㎡あたりに必要な塗料の量(kg/㎡)。メーカー指定の量。 | メーカー技術資料、JASS 18 |
| 希釈率 | 塗料を薄める溶剤(シンナー/水)の割合。規定以上の希釈は耐久性を損なう。 | 塗料メーカー技術資料 |
| 工程間乾燥時間 | 各工程(下塗→中塗→上塗)間で必要な乾燥時間。 | JASS 18 |
塗料は3回塗りで耐久性を確保し、中塗り・上塗りは、長期間美観や機能性を保持するために、均一な塗膜の厚さが必要です。
付帯部の計上漏れ防止リスト
外壁面積に含まれない付帯部の塗装は、劣化防止のために不可欠です。見積書で「付帯部一式」とされ、内容が曖昧になりがちです。特に以下の項目が、適切な数量(mまたは㎡)と単価で計上されているか確認しましょう。
| 部位 | 役割 | 見積もり単位 |
|---|---|---|
| 雨樋(あまどい) | 雨水を排水。塩ビ製が多く、紫外線で劣化する(耐用年数約20年)。 | m(延長) |
| 軒天(のきてん) | 屋根裏の換気・防火機能。 | ㎡(面積) |
| 破風(はふ)/鼻隠し | 屋根の側面部。雨や風から建物を保護。 | m(延長) |
| 庇(ひさし)・霧除け | 窓や玄関の上部で雨除けの役割。金属部のサビに注意。 | 箇所または㎡ |
| 戸袋・雨戸 | 鉄部(サビ対策)または木部。 | 箇所または㎡ |
| 水切り | 基礎と外壁の境目。金属製でサビが発生しやすい。 | m(延長) |
| 換気フード・排気口 | 外壁に付属する金属製フード。サビ止め処理が必要。 | 箇所 |
| 基礎巾木 | 基礎の立ち上がり部分。基礎専用塗料(無機質系)を推奨。 | m(延長) |
シーリングの落とし穴:三面接着防止と高耐久化

シーリング(コーキング)は、サイディングの目地や窓枠周りからの水の浸入を防ぐ重要な工程です。見積もりでシーリングが「一式」になっている場合、最も危険な落とし穴が潜んでいます。
シーリング材のグレードと耐久性
シーリング材は、塗料の耐久性(例:フッ素15年、無機20年)に合わせて、高耐久なグレードを選ぶべきです。
- ・高耐久シーリング材:耐久性が15年~30年に及ぶものもあります(例: オートンイクシード、ジョイントエンペラー)。これらは通常のシーリング材(5~10年で劣化)に比べ、耐候性が格段に高い(例:促進耐候性試験で一般材が5,000時間で劣化に対し、ジョイントエンペラーは6,000時間でも問題なし)。
必須の施工仕様
- 1. 打ち替えの徹底:既存のシーリング材をすべて撤去し、新しい材を充填する「打ち替え」が原則です。既存の上に重ねる「増し打ち」は耐久性が劣ります。
- 2. プライマー塗布:新しいシーリング材を充填する前に、必ずプライマーを塗布し、外壁材との密着性を高める必要があります。
- 3. 三面接着の防止:目地底面と両側面の3面にシーリング材が接着してしまう状態(三面接着)になると、建物の動きに追従できず、早期にひび割れ(破断)が発生します。底面にボンドブレーカー(絶縁テープ)を貼って2面のみの接着(二面接着)にする施工が必須です。
相見積もりの条件統一テンプレート
複数の業者から見積もりを取る際は、価格だけでなく、工事内容と仕様を完全に揃えて比較する必要があります。
《相見積比較表》A社/B社/C社の比較
相見積もりを比較する際は、総額、各内訳の割合、そして年間コスト(LCC)を比較しましょう。
| 項目 | 単位 | A社(シリコン) | B社(フッ素) | C社(無機ハイブリッド) | 比較ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁面積(㎡) | ㎡ | 130㎡ | 140㎡ | 135㎡ | 面積の計測方法を統一させる。 |
| 足場費(㎡) | ㎡ | 1,200円 | 1,000円 | 1,500円 | 単価が高い業者は仮設費をサービスしていないか。 |
| シーリング単価(m) | m | 1,000円/m(変性シリコン) | 1,300円/m(高耐久材) | 1,600円/m(高耐久材) | 高耐久シーリング材の採用有無。 |
| 塗料名/グレード | - | シリコン/10年耐久 | フッ素/15年耐久 | 無機/20年耐久 | 耐用年数の違いを明確化する。 |
| 塗装総額(円) | 式 | 950,000円 | 1,300,000円 | 1,600,000円 | - |
| 付帯部総額(円) | 式 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 付帯部の項目漏れがないか。 |
| 総額(足場含む) | 式 | 1,350,000円 | 1,750,000円 | 2,100,000円 | - |
| 年間コスト | 円/年 | 135,000円/年 | 116,667円/年 | 105,000円/年 | 長期的に最も経済的なのはC社(期待年数で割る)。 |
相見積を同条件化するフォーマット再提出の依頼
見積書の内容が異なり比較が難しい場合は、各業者に対して「(例:シリコン塗料、シーリング打ち替え、高圧洗浄を含む)同条件の仕様」で見積もりを再提出するよう依頼しましょう。
レッドフラッグ12:悪徳業者を見抜く警告サイン

見積書や営業手法に以下の兆候が見られる場合、手抜き工事やトラブルにつながるレッドフラッグである可能性が高いです。
| No. | レッドフラッグ | 理由とリスク |
|---|---|---|
| 1 | 「一式」表記が多発している | 数量や単価が曖昧なため、手抜きや過剰請求の温床になる。 |
| 2 | 単位(㎡、m、箇所)や数量の記載がない | どの範囲にどれだけの材料を使ったか検証できず、手抜きを誘発。 |
| 3 | 塗料の製品名やメーカー名が不明 | 汎用的な低グレード塗料を使ったり、規定量より薄めて使われたりするリスクがある。 |
| 4 | 「足場代無料」や抱き合わせ値引き | 見積総額に最初から足場代を上乗せし、後から「値引き」として提示している場合が多い。 |
| 5 | 即決を迫る大幅な特価 | 考える時間を与えず契約させる手法。手抜きや高額契約につながる。 |
| 6 | 極端に総額が安い(または高い) | 安すぎる場合は下地処理や塗装回数を省略している可能性が高い。高すぎる場合は中間マージンや不当な請求の可能性がある。 |
| 7 | 保証書に但書や除外項目が過多 | 実際には適用されない条件(例: 自然災害、経年劣化)が多すぎて保証の意味がない。 |
| 8 | 工程間の乾燥時間が短すぎる | メーカー指定の乾燥時間を守らないと、塗料本来の性能(密着性、耐久性)が発揮されない。 |
| 9 | 現場調査報告書がない | 劣化状況(ひび割れ、剥離、含水率)を把握せず、適切な下地補修が行われない。 |
| 10 | 自社施工を謳っていない(下請け構造) | 元請けと下請けが何層にもなると、中間マージンが高くなる上に、品質管理が疎かになりやすい。手抜き工事の温床になりがち。 |
| 11 | 「諸経費」が20%を超える | 一般的な目安(5〜10%)を大幅に超える場合、不当な利益計上の可能性がある。 |
| 12 | 付帯部塗装にサビ止め(プライマー)の記載がない | 金属部分(雨樋、水切り、シャッター)の塗装前にサビ止めプライマーがないと、早期にサビが発生する。 |
具体例:費用配分目安
ここでは、一般的な戸建て住宅(30坪、40坪)における費用総額の配分目安を示します。この配分比率から大きく外れる見積もりは、内訳を確認すべきサインとなります。
| 費用項目 | 費用配分目安(総額比率) | 30坪総額 130万円の場合(目安) | 40坪総額 170万円の場合(目安) |
|---|---|---|---|
| 仮設・共通仮設(足場・養生) | 20%~30% | 26万円~39万円 | 34万円~51万円 |
| 外壁塗装(塗料・施工) | 40%~55% | 52万円~71.5万円 | 68万円~93.5万円 |
| 付帯部塗装・防水 | 10%~20% | 13万円~26万円 | 17万円~34万円 |
| 下地補修・シーリング | 5%~15%(付帯部等に含むことが多い) | 6.5万円~19.5万円 | 8.5万円~25.5万円 |
| 諸経費・管理費 | 5%~10% | 6.5万円~13万円 | 8.5万円~17万円 |
※上記は一般的なシリコン塗料を用いた場合の目安であり、高耐久塗料(フッ素、無機)やモルタル外壁の特殊補修(Vカット+シーリング)が必要な場合は、下地補修や塗装の割合が上昇します。
契約〜完了検査チェックシート:品質を最終確認する
工事が完了した際、見積書通りに施工されているか、品質に問題がないかを施主が確認することが重要です。
| 項目 | 確認内容 | 備考 | チェック |
|---|---|---|---|
| 塗膜厚(膜厚) | 規定の膜厚(μm)が確保されているか。 | 塗料メーカーの規定を確認。 | □ |
| ピンホール | 塗膜表面に小さな気泡の穴(ピンホール)がないか。 | 下地処理や乾燥不足が原因となる。 | □ |
| 艶ムラ・色ムラ | 塗料の艶や色が均一に仕上がっているか。 | 塗料の配合や塗り方が不適切だと発生しやすい。 | □ |
| 塗り残し/塗り継ぎ | 外壁の目地、付帯部、入隅(角)などに塗り残しがないか。 | 塗り残しは塗膜の耐久性低下に直結する。 | □ |
| 付着物・異物混入 | 塗膜内にゴミや異物が混入していないか。 | 清掃・養生不足が原因。 | □ |
| シーリング確認 | 目地の深さ、三面接着になっていないか。 | 高耐久シーリング材が使われているか確認。 | □ |
| 付帯部確認 | 雨樋、軒天、水切りなどにサビや剥がれがないか。 | 付帯部の裏側や金具部分まで丁寧に塗装されているか。 | □ |
| 清掃・残材処分 | 現場が整理整頓され、廃材が適切に処分されているか。 | 廃材処分費が見積もりに含まれているか確認。 | □ |
| 保証書 | 契約通りの内容(期間、対象範囲)で発行されたか。 | - | □ |
| いいい | いいい | いいい | □ |
| いいい | いいい | いいい | □ |
FAQ10(よくある質問10選)

Q1. 見積書に「一式」が多いのはなぜですか?
A. 「一式」は、細かな計算を省略したり、現場で変動する可能性がある作業を一括したりするために使われますが、悪質な業者はこれを内訳を隠蔽し、不当な利益を上乗せするために利用します。お客様が内容を理解しにくくなることが最大の問題です。
Q2. 塗料名が「シリコン」としか書かれていません。問題ありますか?
A. 大いに問題があります。シリコン樹脂塗料だけでも数十種類あり、同じシリコンでも樹脂含有量(例:3%と30%)や水性/油性の違いで耐久性や価格が大きく異なります。メーカー名と製品名を必ず確認し、性能を把握しましょう。
Q3. 「足場代無料」と言われましたが信用して大丈夫ですか?
A. ほとんどの場合、「無料」ではなく、本来足場代として計上されるべき費用が、塗装費や管理費などに上乗せされているだけです。足場は安全対策(労働安全衛生法)上不可欠なものであり、「無料」という言葉で契約を急がせる営業トークには警戒が必要です。
Q4. 諸経費の相場はどれくらいが妥当ですか?
A. 諸経費は一般的に総額の5%〜10%程度が目安です。これが20%を超えるなど極端に高い場合は、不明瞭な管理費や不当な中間マージンが含まれている可能性があります。
Q5. シーリングは「増し打ち」と「打ち替え」のどちらが良いですか?
A. 打ち替え(既存撤去+新材充填)が原則です。増し打ちはコストが安いですが、既存材の劣化がひどい場合、すぐに剥がれてしまうリスクがあります。塗膜の耐久性(15年~30年)に合わせるには、必ず打ち替えを選択し、高耐久シーリング材を使うべきです。
Q6. 相見積もりで金額が1.5倍も違いますが、なぜですか?
A. 外壁塗装の費用は、業者(ハウスメーカーか塗装専門店か)、使用塗料、工法の違いにより、1.5倍以上の差が出ることは珍しくありません。リフォーム営業会社は、塗装工事店よりも高額になる傾向があります。金額差の主な原因は、塗料グレードと中間マージンの有無です。
Q7. 下地補修とは具体的に何をするのですか?
A. 下地補修とは、塗装前に外壁材(素地)が塗装できる状態にするための準備作業です。具体的には、ひび割れ(クラック)の補修、塗膜の浮き・剥がれの除去(ケレン=素地調整)、サビ落としなどが含まれます。適切な下地補修がないと、どんな高性能な塗料を使っても1〜2年で剥がれてしまう可能性があります。
Q8. 工事完了後に塗膜の仕上がりを確認するポイントはありますか?
A. 塗り残し(特に目地や入隅)、艶ムラ・色ムラがないか、ピンホール(塗膜の小さな穴)がないかを目視で確認しましょう。契約時の仕様(色、艶)と照らし合わせ、不備があれば業者に手直しを依頼します。
Q9. 契約書ではどのような項目をチェックすべきですか?
A. 契約書には、工事名、工事場所、請負金額、支払い条件、保証内容が全て記載されているかをチェックします。口頭での約束ではなく、必ず書面で内容を確認しましょう。
Q10. 塗料の「規定塗布量」を守っているかを確認できますか?
A. 規定塗布量は、塗料メーカーが性能を最大限に発揮するために定めた「1㎡あたりに必要な塗料の量」です。施主が立ち会うのは難しいですが、施工中の現場で塗料の缶数が面積に対して足りているか確認したり、業者に塗布量記録(写真)の提出を依頼したりすることで、間接的にチェックできます。
まとめ&今すぐできる3アクション
まとめ
外壁塗装の成功は、適切な塗料選びと同じくらい、見積書の透明性にかかっています。
「一式」と記載された曖昧な費用を許さず、数量、単価、仕様を詳細に開示させることで、複数の見積もりを公平に比較することが可能になります。
特に下地補修とシーリング工事は、塗膜の耐久性を左右する隠れた重要項目であり、その内容と使用材料を必ず確認しましょう。
長期的な住まいの安心を守るため、お客様自身が知識を持ち、賢い選択をすることが重要です。
今すぐできる3アクション
- 1. 「一式」の分解依頼:見積書に「一式」表記があれば、すぐに業者に対し数量と単価による内訳の分解を依頼しましょう。
- 2. 同条件テンプレ再提出:複数の見積もりを比較するため、当記事のチェックリストに基づき、塗料名やシーリング仕様を統一した同条件の見積もりを再提出してもらうよう依頼する。
- 3. 実測立会い・写真添付の要求:契約前に、外壁面積(㎡)やシーリングの延長(m)の実測に立ち会うか、施工写真(特に下地処理、下塗り)を工程ごとに残すよう依頼し、手抜きのない施工を担保しましょう。









